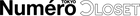Planet Journal 惑星日記 山崎美弥子|vol.5 気づかない不思議
「1000年後の未来の風景」を描き続けるアーティスト山崎美弥子がハワイの小さな離島から送るフォトエッセイ。

流れる川のような美しい白髪の友。我が子を失ったことがある彼女は、人生が「気づかない不思議」で満ちていることを語った。その瞳は決して悲しみに染まってはいなく、ただこの世界の全てを知り尽くしたかのような優しい色をしていた。祖国の深緑の島を、海辺の扉から一緒に見つめた朝のことだった。

…いつも、わたしたちの日々の真ん中に在った一枚の海と空の絵。その絵は、長女キラカイが、この惑星にやって来る少し前、わたしが彼女をからだに宿しながら描いた絵。オパール色にゆらめきながら、水平線から放射状に天へと突き刺すひかりの絵。そのひかりは胸の奥の泉からこんこんと湧き出す、すべての人の内側から生まれ、放たれる「やわらかさ」でもあった。

やがて次女タマラカイが生まれた。ふたりの娘たちが、はじめて瞬きをして、はじめて歩き、はじめて唇からつたない言葉をこぼすようになり、はじめてバースデーケーキを頬張った、サンダルウッドの丘の家のリビングルーム。その壁に、どんな時でも変わることなく掛けられていたその絵。蓋つきのバスケットに入れられ、もらわれてきた子猫のカリキは、その絵の前に据えられた白いカバーの椅子の上で、喉を鳴らして寝転ぶのが好きだった。ひとつの「気づかない不思議」に導かれるかのように、サンダルウッドの丘の家から天国131番地の家にわたしたちが移り住んだ時も、その絵はピックアップトラックの荷台に乗せられ、再びあたらしい住まいの壁に掛けられた。それまでと同じように、わたしたちのそばに在り続け、すべてを見守ってくれた。窓枠越しに、来る日も水平線を見つめ、この島の女神が吹かせる風を存分に深呼吸してきた一枚の絵。そう、たとえ誰かに望まれても、娘たちが決して手放したくないと、
「ノー」
と、口を揃えた一枚の絵。そんな絵が遂に旅立ってゆくことになった。それは今から12ヵ月を7回ほど遡った頃のことだったと思う。波の向こうへ。この絵をきっと、これからいつも、空気のようにここちよく感じてくれるであろう人たちのもとへ。なぜなら、生まれて初めてふたりの娘たちが
「オーケー」
…と言ったから。それはまるで、あの日の彼女たちが、少女であることをいつかやめ、本当に少しづつ、目には見えない人生という時の中の守られた港から、大きな海へと船出する準備を始めたかもしれない証のような出来事だった。祝福であり、ほのかな淋しさを纏う南国の花の香のようでもあった。

12歳と9歳だった二人。大人びてさえいないけれど、決してもう幼な過ぎるわけでもなかった。ぽっかりと、その絵が外された天国131番地の家の壁にはまだ、気配が残っていた。絵を見つめる彼女たちの眼差しの面影も残っていた。わたしはあの日、二人と約束をした。描き続けることを、ずっとこの壁をあたらしいぬくもりで満たすことを。終わることなく、初めから此処に遍満するものをかたちどり、解き放っていくことを。

窓枠の外には夜の始まりの色が宝石のようにまたたく。白い壁をふりかえった、わたしの背中を見つめているのは流星たち。かがやきに再び出会うまで。送り出した一枚の海と空の絵を見つめるあたらしい眼差したちの日々が、きっとその温度に留まり深まっていくことを祈るように思ってみる。この島の涙のようにあたたかい風を頬に感じながら。
そう、美しき友が語った「気づかない不思議」という言葉を、そして、その時のかけらを思う時、この惑星で起きるあらゆること、数えきれないこころたちのいびつさが、パズルがぴったり合わさるように、安心できる居場所にいつか辿り着くことを知った。
とうの昔に子猫であることをやめ、おとな猫になったカリキのふたつのビー玉も、流星と一緒にわたしを見つめていた。

Photos&Text:YAMAZAKI MIYAKO
Instagram:@miyakoyamazaki