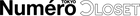Planet Journal 惑星日記 山崎美弥子|vol.8 祈り在り
「1000年後の未来の風景」を描き続けるアーティスト山崎美弥子がハワイの小さな離島から送るフォトエッセイ。
 「アローハ」
「アローハ」
…天国131番地の家の、ライムイエローの午後のこと。誰かが呼びかける声が聞こえてきた。閉ざした門からパーキングまで、200メートルはある。…クルマのエンジンを止める音は聞こえてこなかった。ということは、声の主が門を手で開け、徒歩で丘を登ってきたことがわかる。門を閉ざしているのは、訪問者を締め出すためではなく、大切に育てている花や作物を、空腹の鹿の群れから守るため。

「すぐ行くわ」
叫ぶようにわたしは応えた。扉を開けて訪問者を確かめようと外へ出る。洗濯物を取り込んでいたタマラカイも、聞きなれない声の主を、ひと目拝もうと顔を覗かせた。小さいたれ耳ブラウンと、モップみたいにふさふさ黒の、デコボコ犬コンビも、一目散に走ってきた。まるでアメリカンコミックのキャラクターみたいに。コマの中に描くとしたら、犬たち色で流星が勢いよく尾を引くような図柄になるだろう。二匹は何かが起こると必ず、大袈裟なほど超特急で駆けつけるのだけど、この日ももちろん例外ではなかった。
ついでにトラックの隣では、馬の柵から脱出する方法を覚えてしまい、それは楽しそうに、そこら中を走り回っているキャラメル色の毛並みをした、ハワイアンポニーのキャムが、得意げな顔で立っている。キャムは、どこへでも走り回っても構わないわけでは無いのだが、柵の中に戻してもまた脱出、戻してもまた脱出というルーティンを繰り返していたのだ。
さらには、牛みたいな白黒模様、それから玉虫色の翼のアヒルたちまでそこにいた。アヒルたちはおそらく偶然そこに居合わせただけだとわたしは理解した。ということで、声の主のまわりを、わたしとタマラカイと、犬二匹と馬一頭のフルキャストで、偶然とはいえ、アヒルたちまでもが、取り囲むかたちとなった。声の主は見慣れない青年だった。

「はじめまして。アリといいます。何か手伝えることはないですか?」
彼は、囲まれたことにたじろぐ様子も見せず、静かにそう尋ねた。人間や犬たちはともかく、馬やアヒルまでも自分の呼びかけで現れるなんて、(アヒルがいたのは偶然だとしても、それを彼が知る由もない)もしも、それを体験したのがこのわたしだったら…
「ワーオ!これはこれは、大歓迎ね!ありがとう!」
…なんて、さほど得意でもない英語で、ちょっとジョークでも言いたくなりそうなほど、風変わりなシチュエーションなのに?…そんな思考を巡らせながら、中性的な雰囲気を持つ、ちょっと不思議な青年の質問にわたしは応えた。
「手伝い?手伝いが必要なことは山ほどあるわ。鹿よけのフェンスと門の修復、馬の柵もなおさないと。植物や動物の世話に、それからそれから…」
「何かを感じてこの家に来ました」
真っ直ぐな目はそう言い、連絡先のナンバーを残した。彼が去った後、小さな頃から、見通すような感性を持つタマラカイは言った。

「あの人いいね」
それからというもの、時々アリがわたしたちの日々に登場するようになった。クルマがフラットタイヤ(パンク)になった時に迎えに来たり、急に留守にしなくてはならなくなった時に、犬たちと一緒にいてくれたりした。相変わらず、ちょっと不思議さを感じさせる青年だった。船上での人生を選んだレビーと、進学したキラカイがこの家を後にし、ハイスクールに通い、フラやパドリング(アウトリガーカヌー)の練習に忙しいタマラカイを応援しながら、131番地を今や、ひとり守るわたしにとっては、息子ができたみたいに大いに助けられた。

そんなある時、わたしたちの不在中にクルマのライトが破損した。なおすにはそこそこ予算がかかる。まして島では修理工を捕まえるのも一苦労。頭痛のタネが増えた。アリからは音沙汰が無い。もしや彼が破損させ、それを黙っているのではと、少しがっかりした気分になった数週間後、連絡が来た。
「実は鹿にぶつかって…どうすればいいですか?」
…彼の正直さに救われたわたしは、
「仕方がないからもういいわ。でも、これからも手伝ってちょうだい」
少しおどけた口調で、ひと言伝えた。のちのことアリは、島で手伝いをしていたのは西のオーガニックファームだったけど、事情があってそこには滞在できなくなったと。不憫に感じたわたしは、この131番地に招いたものの、どんな環境にも溶け込んでしまう、働き者のアリ青年は引き手あまた、住まわせてもらえるところは島中にあるという。そういうことならと、わたしは招待状を撤回したけど、意外なことに、アリは他でも無い、この131番地に住みたいと言う。
すでにアリは、彼の顔中を隙間のないキスで埋め尽くすのが得意な、ふさふさ黒犬を、弟と呼んでいた。となると、黒より何歳も年上の、ブラウン色したチビ犬は、姉とでも呼ばれるのだろうか。そして、この家に最初に訪れたあの日、そばに馬のキャムが来て嬉しかったと、アヒルたちもいたあのシチュエーションが大好きだったと、無口なアリが言葉少なに初めて語った。

この家を天国131番地と呼び始めたのは、島のミュージシャン、ロノだった。家の設計者サンシャイン氏は、誰もが迎え入れられる祈りの場を意図したと、わたしは感じている。アリ青年も、もしや、そう感じているのかもしれない。
姿の無い色とりどりの風が、歌声のように通り過ぎる家。島の女神、ヒナが吹かせる風。蜃気楼みたいな水平線が見つめる。…これからきっと、惑星の秘密が少しづつ、解き明かされることになるのかもしれない。ゴールドがマジェンダに滲み変わるハウの花のゆらめきを、その時、わたしは感じていた。

Photos&Text:YAMAZAKI MIYAKO
PROFILE
Instagram:@miyakoyamazaki