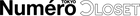Planet Journal 惑星日記 山崎美弥子|vol.10 眩しき孤立の星
「1000年後の未来の風景」を描き続けるアーティスト山崎美弥子がハワイの小さな離島から送るフォトエッセイ。

遠い島へと旅をした。その島は1000年の森の王国であるという。そこは、水の精霊たちの住まうところ。モクレレ(飛行機)の、窓のかたちに切り取られた空は、まるで、曇硝子(くもりガラス)越しの世界のように、ぼんやりと白かった。飛行時間は長過ぎることはなく、夜が小さなその町を青みがかった墨色にほとんど染めてしまう時刻になって、ひとりまたひとりと、地へと橋渡されたタラップを降りていく。こうして、わたしたちは島へ降り立った。到着した小さな空港のバゲッジクレームに、次々と灰色や水色、鴉(カラス)色の荷物たちが乗せられて、その中から見慣れた古いスーツケースを見つけると、しっかり掴んで引っ張って、出口までスルスルと転がした。迎えたのは、まんまるく光った笑顔。わたしたちをクルマに乗せて、宿まで送り届けた。笑顔の中にインテリジェンスを秘めた彼女は、わたしたちのために大切に、野菜サンドウィッチを用意していた。ありがたく頬張りながら、少し笑いあったりした後、…まもなく眠りについた。

とある賢者が語ったことには、この島の奥深くには、聳え立つ山々があるという。その中でも一番高い山は、何か聖なるものが宿っているかのような佇まいをしているらしい。この島も決して例外ではなく、海と空は、まるでカンバスに描かれた1000年後の未来の風景のように、わたしたちと、他のすべての息づくものたちを見つめながら横たわっている。語ることもなく、いつもと同じように。
この惑星には水が在り、あまたの島々が存在する。わたしたちがこの身体をもってして、生で訪れることができるのは、すべての島々の中の、いったい幾つの島であろうか。

夜のカーテンは、まるで待ち構えていたかのように、それでいてゆったりと開き、夜色の時が終わる頃、大きな雷の音が屋根の上に落っこちた。幸い、落っこちたのは険しいその音だけだった。朝色が、外界から宿の中にも溢れ出して、隅々まですっかり染み込んできても、わたしはまだ、ブランケットのネスト(巣)から、飛び出すことはできなかった。雷で始まったその島の日は、最後まで、わたしを放すことはなかった。
宿からすぐ海辺に辿り着くことができることを知ったのは、二番目の朝だった。建てつけの良くない引き戸をガタガタと開き、路地を右に行ってみる。通りの突き当たりに水平線。ずっと会いたかった人を抱きしめようとする時みたいに、走って近づいてみたけれど、海は少し、わたしにだけ人見知り顔を見せていた。

「この島で食べるところはどこにもない。」と、幾人かが口を揃えて言った。でも、浅い夜のパープルの中に、黄色い灯りをともしたシリウスという名の、気軽なムードのレストランを見つけた。シリウスとは、王のようにまばゆい太陽を除けば、この惑星から見える一番明るい恒星であり、あるところでは、「眩しき孤立の星」と呼ばれるという。そんな星の名がつけられたレストランの看板には文字通り、キラキラした星の飾りが点滅していた。あたたかな笑い声たちは、ラベンダー色のシャドウを落として、裏通りまでこぼれていた。テーブルに並んだ食べ物は、世界一うまいものばかりであった。なかでも最後に頬張った、手作りミルクプリンの艶はまさに記録的なものだった。

さらに、分厚い雲に覆われた木曜日、金曜日、それから土曜日が過ぎ去って、わたしたちは、再びモクレレに搭乗した。その島の滝は、白く勇ましい狼のようだった。ダークグリーン深まる苔むした森を歩けば、とこしえの中に在る、あの懐かしい未来の風景を、思い出さずにはいられない。…涙、流した人。水平線を見つけて、思わず駆け寄ったあの朝のような気持ちで、わたしは彼女を大切に両腕で包み込んだ。そう、大切に。
旅の終わりは、次の旅の始まり。きっとまた、逢える。あの島の水平線と、この島の水平線はひとつに繋がっている。コバルトブルーにどんどんと珊瑚色が混ざり溶けていく様を、ずっとわたしたちは上空から見つめていた。
 Photos&Text:YAMAZAKI MIYAKO
Photos&Text:YAMAZAKI MIYAKO
山崎美弥子|Miyako Yamazaki
アーティスト。東京都生まれ。多摩美術大学絵画科卒業後、東京を拠点に国内外で作品を発表。2004年から太平洋で船上生活を始め、現在は人口わずか7000人のハワイの離島で1000年後の未来の風景をカンバスに描き続けている。著書に『モロカイ島の日々』(リトルモア)、『ゴールドはパープルを愛してる』(赤々舎)などがある。
Instagram:@miyakoyamazaki