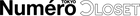Planet Journal 惑星日記 山崎美弥子|惑星の上で
「1000年後の未来の風景」を描き続けるアーティスト山崎美弥子がハワイの小さな離島から送るフォトエッセイ番外編。

夜明けまえと日暮れあと、天国131番地の家があるこの丘には、野生の鹿たちが訪れる。彼らは時に、五十頭あまりもの群れになってやって来る。八十年代にこの土地を手に入れた、サンシャインという名の米国人アーキテクトが、この家を、寺、さもなくば神殿のように、シンメトリックにデザインした。全てが対称的に配置され、大きく野外へと開かれたラナイ(ベランダ)が四方に漏れなく付いている。スライディングドアーの底はわずかに宙に浮き、サッシュは無く、ラナイとリビングルームのフロアはひとつの面に繋がる。だからまるで、四六時中、野外で暮らしているかのような解放感に満ちている。わたしたちはサンシャイン氏との面識は無く、彼とのカンバセーションを楽しむことはできなかったけれど、願わくは、彼の思いに耳を傾けてみたかった。すべての戸を開け放てば、外の世界が家の中に一斉に流れ込み、わたしたちは潮風と共に風景と一体になれる…そんな家。

“彼の家づくりへの思いは当時から
サスティナブルであったことが伺えた”
わたしたちが初めてここにやって来た時には、サンシャイン氏の置き土産、さまざまな宝物がそこここに残されているのが見つかった。絶滅危惧種の希少なウィリウィリ(ハワイアンサンダルウッド)の種の、黄色っぽいもの、えんじ色、朱色、その中間の色…色とりどりが満杯になったジャー(瓶)。裏山へ入り、時間をかけて拾い集めたものに違い無い。古い機織り機と、織糸。織りあげられた素朴なタペストリーはきっと、サンシャイン夫人が手がけたものなのだろう。島の物語ばかりが集められた書籍のコレクション。クラシックとハワイアンミュージックのCD。狩りをし、備蓄のために捌いた後の鹿の角。在来種であるミロの木から掘られた蓋つきの器。ビーチへ行くたびに少しずつ持ち帰って来たのであろう、キリがないほど沢山の、ピンクのグラデーションの小さな貝たち。木製のアウトリガーカヌーの櫂。ディテールから、彼の家づくりへの思いは当時からサスティナブルであったことが伺えた。節水に配慮され、バスタブはとても小さいものが選ばれていたし、キッチンのグレイウォーター(排水)はエントランス脇の、甘いチェリーが実る木の根元にそそがれるように配管されていた。これは、かつてサンダルウッドの丘にレビーが家を建てた時にも採用したテクニックだった。すべてがシンプルに美しく、そしてコンパクトだった。レビーはさらに、シャワーのグレイウォーターも、シトラスの木やニウ(バナナ)の木を新たにわたしたちが植えたところへ流れるように手を加えた。

“サラサラとした木綿のブランケットは
いつもわたしたちの日焼けした裸足に心地が良かった”
イーストからウエストへと絵筆を滑らせたような水平線に、夜のとばりが落ちてしまうと、山側のラナイに置いたデイベッドを寝床にして、横になってふたりで本を読む。それがわたしと、まだあどけなさが残る九歳の頃のタマラカイとのルーティンだった。一枚のブランケットの下に一緒に滑り込む時は、いつも楽しさが胸いっぱいに溢れ出し、ふたりでクスクスと笑ってしまうものだった。少しひんやりと、でもサラサラとした木綿のブランケットはいつも私たちの日焼けした裸足に心地が良かった。彼女には、お気に入りの本の物語がたくさんあったけれど、同時に大嫌いな一冊があった。それは…、母鳥と逸れてしまったスパロウの雛鳥が、他種鳥が守る巣に「入れて欲しい」と懇願しながら飛び回る物語。雛鳥はどこへ行っても拒絶されてしまう。もちろん、スパロウの母鳥と再会し、大好きなお母さんの巣で、それはしあわせに眠りに落ちるというハッピーエンディングを、当然、迎えることがわかっていても、そこへ落着するまでのエピソードは、淡々とした言葉で綴られているのにも関わらず、胸をかき乱されるほどにドラマティックに悲劇的で、九歳の少女には耐えられないものだった。この惑星での生における、時に「受容されないこと」の悲しみを、既に彼女の魂は痛いほどに知っていたのかもしれない…。
デイベッドには白いヴェールのようなカヤが垂れ下がり、その柔らかなメッシュは焦げコーヒー色の木の床まで届いている。薄明かりのハーフムーン(半月)。夜の時間のしっとりとした感触は、カヤをすり抜けてわたしたちの頬にダイレクトに届く。その香りには晩涼が潜んでいる。いつも、物語が終わりに近づくに従い、わたしの瞼は、夕暮れのハオレコアの葉が眠るように閉じられてしまい、上瞼と下瞼を引き離そうとするのに全力を尽くさなければならなくなる。そんな葛藤をしながら物語を読み終えると、ようやく安堵し、堂々と瞼をピッタリと閉じて、わたしたちは、ゆっくりとした呼吸を始める。眠りの国へと。そうして、ふたり揃って夢の次元の一歩手前に到着する頃、霧のようなシャドウの中から音もなき音が聞こえて来る。鹿たちだ。音は無いのにはっきりと聞こえる。それは「気配」。そう、わたしたちのすぐそばまで来ている。ラナイには囲いがあるからか、鹿たちはわたしたちがこんなにそばにいることに気づいていない。…たくさんいる。そのことが、気配からわかる。鹿たちの小さなヒズメが、草に触るシャラシャラとした風が微かに届く。突然、何かの拍子に、一頭が甲高い声をあげたのを合図に、いっせいに皆、静かに、でもそれは勢いよく走り去っていった。瞼をわずかに開けて見ると、夜の中から浮かび上がる椰子の葉のグリーンが波打つ様が月明かりに光っていた。
「鹿がいたわね」
わたしの言葉にタマラカイは頷いた。
 “この惑星の上でひとつであることを感じていた”
“この惑星の上でひとつであることを感じていた”
わたしたちは、青い夜の山の中へ、歌声が届く時のようなしなやかさで走り消えていった彼らと、それから、夜から浮かび上がる南国の花々や、月や星や、それ以外の、生きとし生ける万物が、この惑星の上でひとつであることを感じていた。
Photos&Text:YAMAZAKI MIYAKO
Instagram:@miyakoyamazaki
※こちらのエッセイは、株式会社ワコールのために作成され、同サイトにて2024年9月30日まで掲出されていたものです。